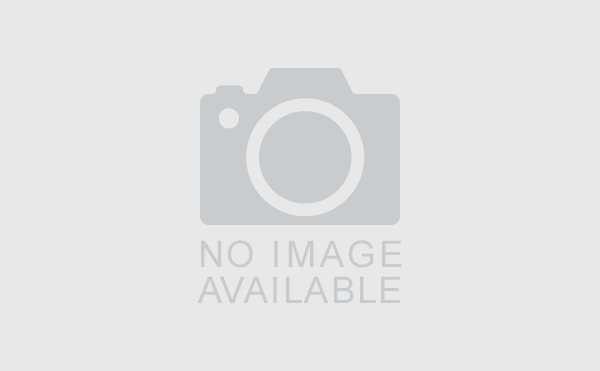【まちなかの散歩:92】『旅』(2016年4月)
旅に出ると、至るところで春休みを利用した沢山の学生の旅行姿を目にする。それは今も昔も変わらないのだが、昨今は高齢者集団の多さと外国とりわけ中国・韓国の観光客の多さが際立つ。本紙の『豊中への便り』欄にあるように、中国人が大きな声で話し、集団をなして我が物顔で歩くのは、少し前の日本人と同じだと理解したいのだが、紳士になった初老の私には、正直いささか敬遠したい状況である。
彼ら日本に来る観光客のことを“インバウンド”と呼ぶらしいが、野球で地面の整備が悪くて不規則に跳ねる“イレギュラーバウンド”(不規則バウンド)位しか知らなかった身には、不景気による国内の消費減を補う国策で外国人を迎え入れ消費させたいという観光国際化時代にも乗り遅れそうだ。
そんな中、今年も隣国の旧友がやって来て我が家に滞在した。滞在中に彼が私に質問した内容である。
- 日本が負けた時、皇居前で涙して泣いている写真を見たが、敗戦を日本人は悔しかったのか?
- 満州引き揚げ者が多い中、沢山の中国残留孤児が何故いるのか?
- 福島の事故以来、沢山の日本人が原発反対を言っていたが、今、どうなっているのか?
- 何故、ほとんどの人が原発に反対しているのに政府は推進するのか?さらに輸出までするのか?
- 選挙公約にもない沢山の国民が反対する政策を強引に推進するのに、なぜ政権が変わらないのか?
- 大阪都構想が住民投票で、ぎりぎりとはいえ否定されたのに、首長選挙(知事・市長選)で同じ主張の政党が圧倒的に勝つのか?
- マイナンバ―制度で国民にメリットがないのに、「国民の政党」は反対せず制度が進められるのか?
- 欧米では女性スキャンダルで職を失わないのに日本では失い、金で権力を間違って行使した政治家をTPP協定調印式にいかせようとしたのはなぜか? また議員職を失わないのは何故か?
- 青い胸バッチを付けた国会議員が、何故何年も拉致被害者の問題に全く手を付けないでいるのか?
そんな彼の帰国を待って兵庫県北部の余部(餘部)鉄橋まで足を伸ばす。あの1968(昭和61)年回送中の列車が突風にあおられ8両編成の全車両が転落、橋梁の真下にあったカニ加工場と民家を直撃して車掌と工場の従業員主婦5名が死亡した事故現場である。運転士の上司は責任を感じて自殺した。現橋梁は無機質だが安全面での機能美を誇って2010(平成22)年供用が始まった。旧橋梁は1912(明治45)年3月1日に開通した鋼製トレッスル橋という美しい高架橋であった。日露戦争時に全線開通時に鉄道院で建設されたが、完成当時には駅がなく最寄りの駅まで列車の合間を縫って橋梁とトンネル3つを越えて毎日通学していたという。繰り返し陳情し駅(餘部駅)の設置が決定されると地元の子どもたちは海岸から石を運び上げる作業を手伝っている。現場にはその時の写真が展示されている。
子どもたちが懸命に作業する写真を見ていると、5年が経った東日本大震災からの復興を願う子どもたちのために復興税は活用されているのかと考えてしまう。選挙公約にないことばかりを次々とやり、結果オーライというなら、市民・国民の政治選択の機会である選挙は意味をなさずお任せ民主主義でしかない。役所にお任せといえば、わが豊中市に再生資源の持ち去り禁止条例ができたが、それを生計費としている廃品回収の民間業者に任せれば彼らも稼ぎになり行政も人件費(税金)を他に振り向けられるのに何故直接役所がやるのか。後始末が悪いせいなら、隣人が注意するか後始末すれば良いのではないか?
市民・国民が自ら出来ることはやるから、どうしても公共でなければできないところに税を投入して欲しいものである。そんな思いを抱きながら帰途についた。
(『豊中駅前まちづくりニュース』Vol.171に掲載)
※まちなかの散歩のバックナンバーはこちらをご覧ください。