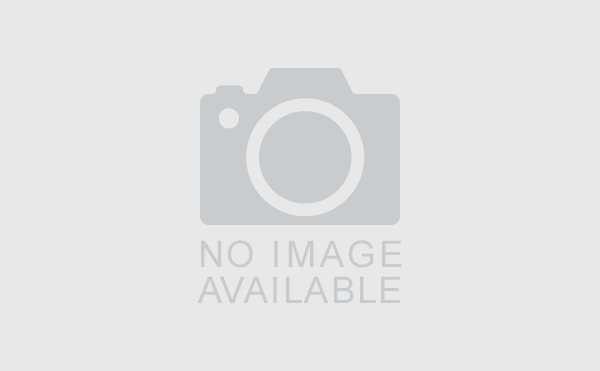【まちなかの散歩:40】夢は枯野を駆け巡る(2011年12月)
師走、12月。年齢を重ねると、その年数を分母とした数字が段々と大きくなり、分子の1年が相対的に小さくなって、1年を早く過ぎると感じるのだとか。まさに、もう年の瀬を迎える。一年の締めくくりの月だが、今年はそう簡単には締めくくれない。
現実に経験せずとも、また阪神淡路大震災の経験者でも更に人生観が変わるという未曾有の災害をもたらした東日本大震災。地震・津波・原発事故から、はや9か月が過ぎようとしているが癒されない傷、定まらないそれぞれの地での復旧・復興。
今月号と来年(来月)1月号は、その締めくくれない思いを紀行文として伝えたい。
駅舎を壊された内陸部の世界遺産・平泉。北上川河口・橋の袂の小学校で命を落とした幼い子どもに宛てた母親の手紙を刻んだ碑。漁業と連携できない復旧・復興住宅。丘の上の病院の一階まで津波に襲われた女川町には建物の底を見せて今なお横たわるビル。原発立地によるものか、人口規模に不相応の体育施設群に仮設住宅が並ぶ。TVで伝えられた3階建てであるが、その生活の行く末は依然として不透明である。前衛芸術のようにビルの上にバスが残る石巻。亡くした家族との思い出を引きずりながら何度も足を運んでいるであろう花と線香が残る仙台市若林地区。塩に浸された田畑への綿花栽培のささやかな試み。なだらかな白砂青松の地は近郊の海水浴場として賑わい、のどかな”誉生”を送ろうとする高齢者を迎え入れた老人ホームの格好の立地場所であったろうに・・・。押し流された長い松並木、土台だけを残して失った建物と人生。左右が泥沼化し嵩上げされた仮設道路を被災物満載の隣県ナンバーのダンプがすれ違う。震災特需でもある。断絶し津波に押し流された線路・駅舎の跡が残る亘理町・山元町。同じ県内とはいえ100キロも離れた会津若松の地で町役場ごと避難所生活を送る原発直近の町、大熊の被災者達。校庭に設置された自動放射能測定器。避難所代わりに使われた温泉宿。風評被害で来なくなった観光客のようやく回復の兆しの象徴である数台の観光バスの姿を口に出し繰り返し喜んでいた友人の姿が印象的である。我々が映像で見る物理的施設の損傷は勿論のことであるが、見えない心の傷は大きく、原発事故による将来への不安とストレスは、傷を一層深く拡げて、想像し難いものがあるという。
“旅を止んで、夢は枯野を駆け巡る”
(『豊中駅前まちづくりニュース』Vol.71に掲載)
※まちなかの散歩のバックナンバーはこちらをご覧ください。