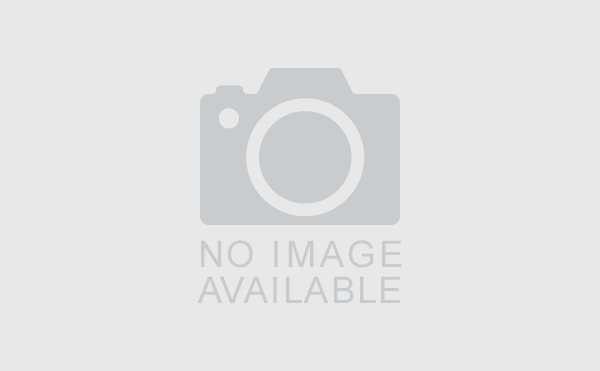【まちなかの散歩:15】まちづくりのDNA(2009年11月)
桐生事件で無罪が証明されることになったことで一躍有名になった「DNA鑑定」による最近の鑑定技術も極めて優れものであるが、小林一三翁、そして、翁のDNAを受け継いだ「阪急100年のまちづくり」の歴史を聞く機会があった。
阪急電車の前身「箕面有馬電気軌道」で有名な箕面の動物園が、周辺への臭い公害で、わずか10年で幕を閉めたこと、宝塚歌劇の最初の舞台として板を置いたのは、温泉の上にではなく、水プールの上であったことなど不勉強であったことを感じながら、その斬新なアイディアで「阪鶴鉄道」の後始末という後ろ向きの仕事を前向きに取り組み、「鉄道と住宅地経営」として展開して、苦境を見事に切り抜け、その精神を今日まで、脈々と引き継がせていった一三翁の「ロマンと算盤」の話に聞き入っていた。
阪急宝塚沿線を中心に「阪急平野」と呼ぶこともあるが、その中心にある豊中で半生を送って来た者にとって興味深い話であった。そして、かつて、ボンネット型の村営バスを走らせていた桜井谷村(注)の心意気を思い出していた。
自らを省みて、若い頃に薫陶を受けた職場の上司、師匠のDNAをどこまで受け継げたのだろうか。まちの歴史もどこまで受け継がれているのか?反省しきりである。
熊本県下益城郡山都町(旧矢部町)に現存する通潤橋は、その見事な景観で有名であるが、150年以上も前に、水利が非常に悪く毎日の飲み水にも事欠く貧しい隣地区の白糸台地を潤すために、深い谷を越えて対岸に農業用水を送るために計画された。いかに高く谷を越えるかという石橋の技術、いかにロスなく水を送るかという管水路の技術を組み合わせ、逆サイフォンの仕組みを採用し、地元の水準の高い石工を中心に広い範囲から石工を集め、地元からの資金調達に加え、藩からの財政的支援を受け、庄屋のまとめ役・地域リーダーである惣庄屋布田保之助の陣頭指揮の下、100haに及ぶ不毛の台地を田畑として灌漑し、貧しくて身売りを余儀なくされていた地域社会を救ったという。
しかも、その技術は江戸の万世橋・浅草橋等の架橋として広められている。まさに、その美しい景観もさることながら、その背景にある地域社会におけるリーダーの優れた企画・強い意思、生活環境改善の技術・仕組み、矢部郷住民の献金と労力奉仕という地域社会での合意、藩の財政支援を説得する理論武装と藩の理解・・・、という総力戦であり、また、そのノウハウ・技術の普及・継承・伝播がある。まさに「まちづくりの原点」ではなかろうか。
(注)桜井谷村 豊中市の北部、現在中国自動車道沿いの地域で、大阪大学がある待兼山町のほか柴原町、桜の町、春日町、緑ヶ丘、上野西町、刀根山などが含まれる。1910年開通の阪急宝塚線、豊中駅開通にあわせて、桜井谷村は独自に村から豊中駅までの村営バスを走らせ、時代の変化に対応していた。後に村営バスは阪急バスに吸収される。1936年に、同村は豊中町と合併し、豊中市が誕生する。
(『豊中駅前まちづくりニュース』Vol.23に掲載)
※まちなかの散歩のバックナンバーはこちらをご覧ください。