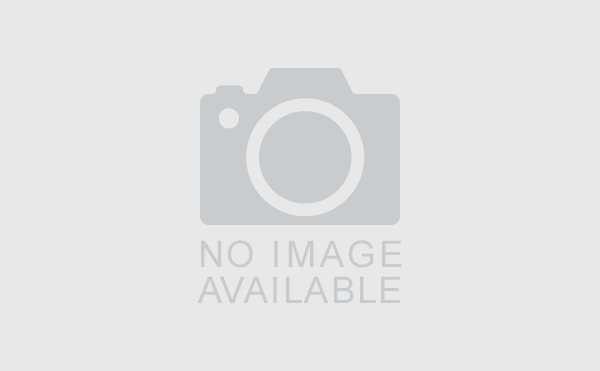【まちなかの散歩:139】寒い寒い春である(2020年3月)
2月初めの暖かな朝、散歩道で梅の花を発見。冤罪で大宰府に流された菅原道真の身の上に思いを遣りながら「早くも冬を越えたのか」と感慨に耽った。しかし数日後には、ぴゅうぴゅうと激しい風が吹く寒波に襲われ、一瞬ではあったが雪もチラつき旭川ではマイナス36度を記録する日を経験した。極端から極端に走る現代の世相に極似する。いやはや。
寒くなるのは気候ばかりではなかった。まちもメディアも新型コロナウイルス(肺炎)の恐怖一色で、大半の方がマスク姿になっており背筋が寒々とした風景を見せていた。それは消費税増税の影響で落ち込んだ日本景気を支えて海外勤務で苦労する企業戦士たちと、老後を海外で楽しんでいる家族をも直撃した。上海駐在の知人は家族を日本に帰し自宅待機だとか。グローバル化の負の現実である。
一方、蓄え乏しい年金生活者にとって、これまで唯一の楽しみであったTV番組が、今ではNHKの深夜までもお笑いタレントに独占され、ドラマも旅番組も再放送が流され、犯人を知っていては新鮮味がなくつまらない。そんな時間を持て余してしまう身でも抵抗力弱い身では外出もままならず、若い頃に読み切れなかった“積ん読書”を弱ってきた視力を駆使して時間を潰すこととする。恋と悪遊びは記憶に残るが、忘却の彼方にあった教科書の復刻版が出ていて懐かしい。
頁を開けば、民主主義、基本的人権、主権在民、戦争放棄、三権分立、国会の国権の最高機関、勤労者の団結権・団体行動権の保障、国民の文化的な最低限度の生活の権利、最高裁判所の違憲審査権限、公務員の国民全体の奉仕者、集会結社の自由などの言葉が並ぶ。
そういえば、戦後のアメリカ民主主義教育で育った我々世代はホームルームの時間があり、クラスでテーマを決めて全員で議論をしたものである。ゆとり教育の反動で情報習得・詰込みが求められ時間の制約で最近は学校でやらないのだろうか。最近は近づかなくなってきた孫たちに尋ねてみよう。さらに進学すると“ディベート”もやった。議論のための議論ではあったが、テーマを決めて自分の本来の意見とは違っても肯定派・否定派にあえて分かれての討論形式での議論を学んだものだ。現代の学校教育でも実践されているのだろうか?アメリカが教えてくれた民主主義教育の基本的な訓練だったと今思う。
ラインやツイッターでの自分の感想だけを言いつのる簡単な主張が跳躍跋扈する。他人の意見には耳を傾けない姿勢が格好いいという。「話せばわかる!」を聞き入れなかった行動を許した言論封殺の思想。熟議民主主義の軽視。2月は2・26事件が起こされた月でもある。
『平家物語』を真似てみる。“遠く異朝をとぶらへば”、トランプの弾劾裁判は議論抜きの多数決での無罪とされ、我々が学んだ“アメリカン・デモクラシー”はどこに行ったのだろうか?と“世界の警察”を放棄したアメリカの国の様変わりに寒さを覚える。“近く本朝をうかがふに”森友を失い、加計を活かし家計を狂わす。桜を散らせ、三権を思うままにして民間の憂うるところを知らざりし者ども、おごれる心もたけきことも皆とりどりにありしかども“心も詞も及ばれぬ。” “ならぬことはならぬのじゃ!”
奇しくも2月8日は、豊中市野田地区で計画された「森友学園」の問題が取り上げられた日であった。一時はマスコミ陣が取り巻いていた豊中本町の籠池邸も話題に上がらなくなっている。日大理事長がアメフト問題で「放っておけばみんな忘れるよ」と言い放った言葉が耳を離れない。現状はそのとおりである。♪回る回るよ時代は回る♪と諦めて居直りを認めておればいいのだろうか? “過ちて改めざる、これを過ちという” 「カエルの面にしょんべん」「糠に釘」「暖簾に腕押し」我が田舎では「肥持ちに屁」ともいう。いやはや。季節は春だが、寒々とする世相である。
(『豊中駅前まちづくりニュース』Vol.238に掲載)
※まちなかの散歩のバックナンバーはこちらをご覧ください。