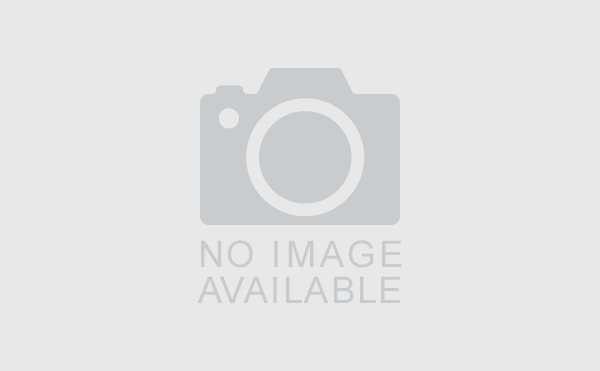【まちなかの散歩:67】仏壇(2014年3月)
今年も3月9日から23日まで開催される大相撲・大阪場所の合宿所として豊中稲荷神社に荒汐部屋がやってきた。復活した中国・内モンゴル出身の男前の蒼国来(そうこくらい)、1月場所で序の口優勝した介護福祉士の資格を持つ変り種の突光力(とっとうりき)をはじめとする力士のまげ姿が豊中駅前で見られることだろう。
さて、その相撲の決まり手は、かつては四十八手(しじゅうはって)とされていたが、これは正確な決まり手の数字ではなく、「相撲の技の数は多い」「縁起よく48」などという意味だったという。現在は、決まり手82と非技5つ(勇み足、腰砕け、つき手、つき膝、踏み出し)となっているが、滅多に決まらないため“幻の決まり手”とも呼ばれている豪快な技の一つに「呼び戻し」がある。かつては「揺り戻し」や「寄り戻し」とも呼ばれ、最近では昨年9月場所で横綱白鵬が幕内では16年ぶりに決め手としたが、我々昭和の相撲ファンには若ノ花の「仏壇返し」として記憶にある決め手である。
アメリカの仲介で首脳会談を進めようとする日韓両国であるが、年長者・先祖を敬うことでは日本の比ではないとされてきた韓国で、息子を通じての家督相続の考え方に急激な変化が起きているらしい。電車内では、ほとんど例外なく年長者に席を譲ることは既に経験していたが、グループで韓国を訪問した時、友人宅で家族料理を頂く段になって、年嵩の男(家長)がまず先に食事に手を付け、それから年下の男子、その後で妻・子の女性が食べるように指示した友人の父に驚いたものだが、最近の韓国の若い世代には家系の継承を固守しなくなっているのだという。多くの両親は息子よりも娘を選んでいるという。親達が娘達の世話を期待しているからだとか。長く続いてきた家系の継承という考え方が急速に消えていくということは信じられないことである。
日本においても、すでにそういう現象は起きていて、親父役の声優が亡くなって話題になったサザエさんの漫画からとった“マスオさん現象”がそれであり、微笑ましい昭和の家庭でもある。豊中駅前でも2家族が住んでおられることが窺える表札を拝見することも少なくない。
祀継承者として我が家の古くからの仏壇を守ってきた私の身にも、同様の事情が生じてきており、遅ればせながら、えらい時代になって来ているのだと身をもって感じざるを得ない。誰かに“仏壇返し”ができるわけもなく、お寺に永代供養を頼まなければならなくなるのだろうか? 稲荷神社での厳しい朝稽古の声を聞きながら、そんな思いが“呼び戻し”となってきた。まもなく春分の日。暑さ寒さも彼岸までか。
(『豊中駅前まちづくりニュース』Vol.123に掲載)
※まちなかの散歩のバックナンバーはこちらをご覧ください。