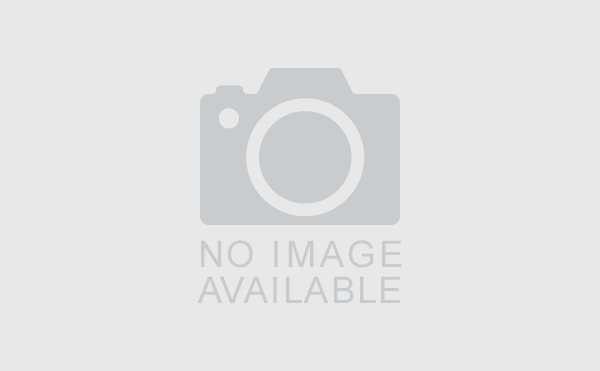【まちなかの散歩:63】冬眠(2013年11月)
夫婦2人きりとなった我が家に孫を誘き寄せる秘策として飼ってきている銭亀の動きが、最近とみに鈍くなってきている。いよいよ冬眠に入るようである。どこか激変する政治状況に対する取り立てた動きを見せない市民・国民の動きに似た感がしてならない、と言っては亀に失礼か。(かめへんか?)
東日本大震災の被害を受けた町から視察の話があった。聞くところでは町の議員全員だという(地元での事故の発生や旅行中の事故時の危機管理はどうなっている?)。
訪問団の責任者は説明中もしきりに時計を見る。2時間の設定にはまだ30分しか経ていない。何処かで見聞きした風景である、1970年の大阪万博工事期間中の視察がそうであったという。有馬温泉に行きたいがために視察を仕立てたということだったとか。
研修を途中で切り上げ、「今日の説明資料を議会事務局あてに送ってくれ。視察報告書を書かねばならないから。」と最後に言って去っていった。390円の送料を要して送った資料に基づき、事務局職員が書くのではないか?視察費も事務局職員の人件費も町の予算から出るはずだ。復興に必要な経費が、このように使われているとすればひどい話である。
石巻市で津波危険区域にやむを得ず戻った人の話をTVで見た。市財政の都合で立ち退き料が出せる地域が限定されているからという。石巻の財政負担が重い。宮城県の財政負担が大きいという。そして復興補助金が使いきれなくて、全国の事業に適当な名目を付けてばら撒かれている。我々は、何のために復興のための税負担をしているのか。
もっと悪質なのは、黒字を誇示する行政の欺瞞である。料金(税金)の前払いをさせる会社(役所)が黒字になる最も簡単な方法は、市民のための仕事・サービスをしないことである。我々は、だまされてはならない。行政の黒字は、仕事をしていないということでもある。市民が提案する事業を推進できない理由の大きなポイントに「財政が苦しいから」という話はよく聞かされる。黒字で財政が苦しいという感覚は、冬でもないのに神経が“冬眠”している。家計同様に国も市も入る金は当然に常に限られている。その限られた金を何にどう使うかが問題で、それを冷静に監視する責任を我々は自らと子孫のために負う。“冬眠”を続けても良いのは亀であって我々“市民”は、「税の行方」の監視をサボるわけにはいかない。
自分のまちの管理を人任せにして、美味しいところだけを喰うという“タダ乗り”が横行するようでは、市や国を市民・国民が自分たちの役立つようにコントロールすることは難しい。市民と市民、市民と行政とが“連携”するだけではなく、担うべき“役割分担”をすることこそが、まちづくりに必要な基本的な考え方ではないだろうか。
(『豊中駅前まちづくりニュース』Vol.116に掲載)
※まちなかの散歩のバックナンバーはこちらをご覧ください。