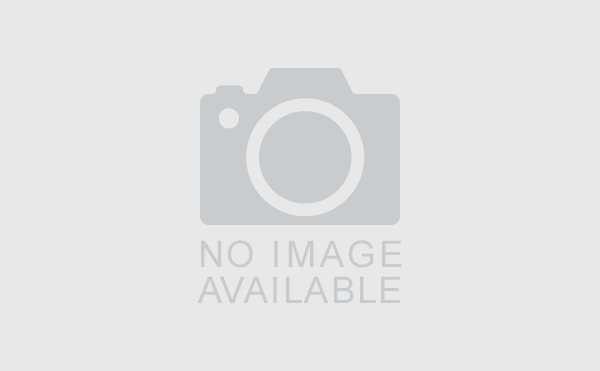【まちなかの散歩:122】「豊中駅前まち歩き」のすすめ(2018年10月)
25年ぶりといわれる超大型台風21号が我が町も襲い、休校・休業・交通機関の計画的運休・停電、そしてテレビのない時間を過ごした。電話の不通は携帯で補える家庭が増えても、オール電化生活での調理(冷蔵庫)・風呂・車庫等への支障が浮かび上がる。都市生活の進展とはどういうことなのか?快適な都市に住む便利さと引き換えの危険を改めて考える。都市防災への先行投資、市民の足・情報を確保する技術的向上と安全性と利便性とのギリギリの両立を図る姿勢を市民は求めている。
そして今、「都市の生活基盤」を取り戻したまち中には、秋のまちづくり会社の恒例となった「丹波ツアー」への参加を心待ちにした方々がおられる。広々とした空の下、四方を穏やかな山並みに囲まれた畑で自然栽培の丹波の黒豆刈りを終え、好評の「ユニトピアささやま」で舌鼓を打ち、綾部に向かう。地域(郡)の発展を蚕糸業に託し、人間教育と優良品の生産を基に会社を巡るすべての関係者との共存共栄(共生)をはかることを経営方針(是)としたグンゼ(郡是)の歴史博物館『グンゼ博物苑』を見学。昔懐かしい下着・ストッキングの会社のルーツ「よい人がよい糸をつくる」精神を識る。そして具体的行動として「あいさつをする」「はきものをそろえる」「そうじをする」を〈三つの躾〉とするという。
この3つを「まちづくり」で表現すると「しくみづくり」「しごとづくり」「施設づくり」である。豊中駅前地区にこれらがどの程度整っているのか。本紙『豊中駅前まちづくりニュース』の紙面上でこれまで何度も、まちづくり(推進)協議会の活動報告欄である「ジャストなうとよなか」「まちづくり掲示板」で取り上げられてきた、住民組織「まちづくり協議会」が作成した『まちづくり構想』、これを受けて豊中市が作成した『まちづくり基本方針』は10年前の作成である。7月の市議会でも各政党の市議会議員から豊中駅前地区の現状を憂う厳しい質問と紋切り型の答弁がなされていた。「10年が経過した計画」という答弁表現は、当事者としての意識がない。「10年を無策に過ごした」と言うべきであろう。
まちづくりの専門家として高名な佐藤滋氏の“まちづくり”の定義は「地域社会に存在する資源を基礎として、多様な主体が連携・協力して、身近な居住環境を漸進的に改善し、まちの活力と魅力を高め、「生活の質の向上」を実現するための一連の持続的な活動である」とされる。過日、韓国の自治体職員視察団から「計画が決められているのになぜ実行しないのですか?」と疑問が発せられた。・・・・・・。
10年を無駄に過ごしてしまった「豊中駅前」の現状・問題点を、その歴史とともに確認し、新たに住民となられた方々に「我がまち」を紹介するため第3回「豊中駅前まち歩き」を協議会が企画した。今年もまちづくり会社がお手伝いする。10月27日(土)座学、28日(日)まち歩きで、いずれも午後1時から詳しくは、別欄で紹介する。是非、参加を願いたい。
(『豊中駅前まちづくりニュース』Vol.221に掲載)
※まちなかの散歩のバックナンバーはこちらをご覧ください。